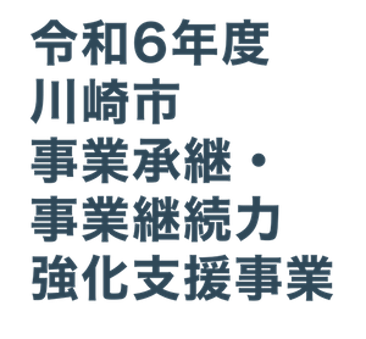【かながわ経済新聞 8月号掲載】

第3回 山次工業
「葛藤」乗り越え新風吹き込む
■人望厚く成長
「幸福な家庭は皆似たり寄ったりだが、不幸な家庭は不幸の理由がそれぞれ異なっている」
言わずと知れたロシアの文豪・トルストイが遺した小説『アンナ・カレーニナ』の冒頭の一文である。事業承継も、家族間の諸問題と切っても切り離せない関係にあるだけに、同じ法則が当てはまるように思われる。難しい承継の背後には往々にして、その家族に特有の悩みが詰まっていると述べても過言でないかもしれない。
2015年にトップ交代を行った山次工業(川崎区)も、父と子の間に横たわる口にはなかなか乗せにくい葛藤を乗り越えて、事業承継を無事に成し遂げたケースである。

山口幸太社長の祖父に当たる山口寛次氏が1966年に開業した同社は、電車に電気を送る架線システムを支える架線鉄柱や、鉄柱同士の上部をつなぐ鉄製ビームの製作を得意とする。東急電鉄向けに高いシェアを誇っており、長らく、都内に本社と工場を構えていた。その後、業容の拡大を受けて83年に川崎区桜本に生産拠点を移転。08年には幸太社長の父、山口和夫氏が寛次氏から経営のバトンを受け継いだ。
和夫社長は若い頃より帝王学を学んでおり、自らを律しながら山次工業の経営に当たった。加えて、周囲からの人望がとみに厚かった。顧客である鉄道会社は東急に限らず、安全と信頼を何よりも重視する。そうした期待にもきちんと応え、11年には4億円を投じて川崎区塩浜に自社新工場を建設するまでになっていた。
■余命10年の宣告
かたや幸太社長はというと、当初はホテルマンになるという夢の実現に向けて、カナダに留学していた。ところがある時、父から唐突に、「私はあと10年の命だから、早く会社に入りなさい」と電話で告げられ、志半ばで日本に帰国せざるを得なくなった。忸怩(じくじ)たる思いは想像に難くない。そして常務として社長を支える日々が始まった。ところが今度は、「会社を商社のようにして、製造は他社に任せたい」という趣旨のことを父が言い出した。14年のことだった。この背景には、鉄道会社の輸送力増強投資が一巡し、これに伴い、会社の売り上げが伸び悩み始めたという事情があった。
しかし、さすがにこの考えには父と言えども、社長と言えども首肯できなかった。お客様である鉄道会社が山次工業に仕事を依頼してくるのは、品質や納期を含め、製造部門を自社で抱える一気通貫こそが強みであるからだった。
「商社になるなんてダメだ」
「それなら社長を辞める」
「では、オレが代わりにやる」
こんな緊迫したやりとりがなされた末、翌15年、急遽3代目として同社を引っ張っていくという想定外の展開になった。心の準備は万端と言ったら、恐らく偽りとなろう。幸太社長自身も「情熱だけで社長になった感じですね」と苦笑しながらこの時を振り返る。
■奮闘の日々
ところで一般にM&A(企業の合併・買収)は合意への歩みよりも、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション=買収・合併後の統合プロセス)が重要だとされる。実は継承事業も、代替わりした後の、新しいトップの振る舞いいかんが成否のカギを大きく握る。幸太社長は、「新しいぶどう酒は新しい革袋に」のことわざ通りに、山次工業に新しい風を呼び入れた。
企業目的、事業目的、経営方針、行動指針などを制定し、社会の公器であるとの姿勢を明確にするとともに、親族が経営に関わらないよう内規を改めた。品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得。 20年には本社も川崎区塩浜に移し、名実ともに川崎に立脚する企業として姿を整えた。
事業運営の面でも、鉄道関係製品の製造販売を引き続き基幹ビジネスに据えつつ、携帯電話基地アンテナの支持構造物の製造といった新規事業の開拓・育成にトップセールスで臨む日々である。川崎市青年工業経営研究(通称・二水会)副会長も務める。財務体質の強化などいくつかの経営課題は残るが、15年に会長に退き、そして逝去した父・和夫氏は息子の奮闘ぶりを草葉の陰から見守っているに違いない。


取材 かながわ経済新聞