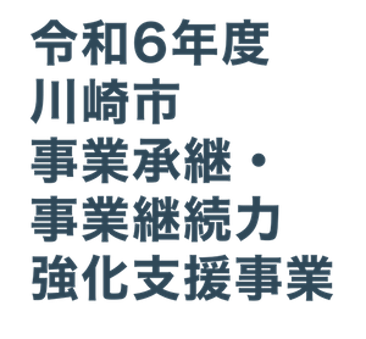【かながわ経済新聞 7月号掲載】

第2回 スタックス
「環境」が人を生み、「気付き」が変える
■もどかしさ抱え…
「孟母三遷」という言葉がある。孟子の母が息子の教育のため、より良い居住環境を求めて三度引っ越した故事にちなみ、人を育てるにはいかに環境が大切かということを説いたことわざだ。もちろん、孟子とまでは至らなくても、環境やポストが人を育てるとはしばしば言われることで、それは、事業承継においても「成功」に欠かせない要素と言える。
今年で設立72年目を迎えた精密板金加工、スタックス(川崎市中原区)も、やはり、要所ごとにおける「環境」が、結果としてスムーズな代替わりをもたらした。
同社は、星野佳史現社長の祖父が、曾祖父と始めた祖業である入浴剤の製造販売事業を他社に売却し、それで得た資金を元に金属加工に特化した大星工業(2001年に現社名に改称)を設立したことに始まる。星野社長は物心付いた頃より祖父から、「将来はお前が会社を経営するんだぞ」と言い聞かされて育ったという。それは、普通は“目に入れても痛くない”と例えられる祖父と孫の関係というよりは、経営トップと幹部のそれに似たものだったそうだ。これが第一の「環境」であった。
ただ、そう言われても自分の人生なのでやすやすとは受け入れらない。星野社長はもどかしい思いを抱いたまま成長し、母が2001年に祖父から経営のバトンを引き継いだ後も、面従腹背的な態度を崩さなかった。趣味であるバンド活動にものめり込んだ。

■腹くくり計画的に
転機が訪れたのは2009年、26歳の時だった。大学を出て、実社会の仕組みや厳しさが分かってくると、自分をここまで不自由なく育ててくれた祖父や母、そしてスタックスで働く従業員の汗と努力の重みが突如、胸に去来した。「恩返しをしなくては…」。そして、皆に報いるには会社と正面から向き合い、入社後は、将来、社長として引っ張 っていかなければならないのだと腹をくくった。「機が熟す」という例えがあるが、星野社長の心がおのずと開く「環境」が訪れるのを、祖父も母もじっと待 ったことが奏功した。
入社後は、ベテランの技術者が数多くいる「環境」のなか、法学部出身の身で技術を無理してキャッチアップすることは無用なあつれきを生みかねないと判断。母の社長業をサポートしながら経営管理の分野に重きを置いて勉強した。金融機関との折衝も率先して行った。川崎市内の中小企業若手経営者や後継者で構成される川崎市青年工業経営研究会(通称:二水会)の門をたたいたのもこの頃だった。これらには、「いつか来る」であろう社長となった時に備えた準備という側面もあった。
しかし、その日の具体化は意外に早か った。65歳、2020年で社長を退きたいとの母の意向を前に、川崎市産業振興財団コーディネーターの助言のもと、 3年がかりで計画的に事業継承を進めることになったからだった。時間的に余裕のある「環境」となったため、結果から先に述べれば継承は「大きな苦労や失敗もなく済んだ」。
■「不易流行」貫く
星野社長が就任後、まず掲げたのが「不易流行」という企業理念だった。言わずと知れた松尾芭蕉の俳諧信条で、意図するところは企業として「変えてはいけないもの」と「変わっていかなくてはならないもの」を峻別して事業に当たろうという決意表明だった。一方で経営には、自ら携わらないと分からない課題や疑問、悩みといったものが必ず存在する。こうした折、二水会のメンバ ーとの交流から得られる「成功のための裏技」や「他では絶対に聞けない話」は、新社長として学ぶ貴重な「環境」であったと振り返る。
なお星野社長は二水会において、歴代で2番目に若い会長職を経験。全国7大都市の青年経営者が一同に会し、経営者としての資質の向上を目指す「大都市青年経営者交流研究大会」の実行委員長という重職も経験している。
こうした一連の経験を踏まえ、星野社長が今取り組もうとしていることの1つが、優秀な技術などがありながら後継者不在を理由に会社を閉じようとしている川崎市内の中小企業を救済するフレームづくりだ。スタックスとの協業や、場合によってはM&Aも辞さないと、ものづくりの街・川崎の未来に熱視線を注ぐ日々である。

取材 かながわ経済新聞