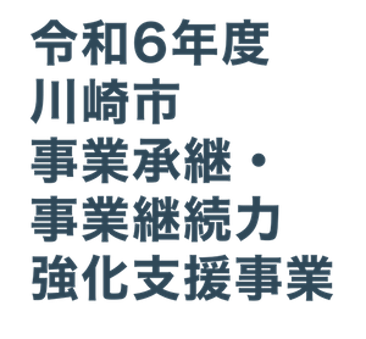【かながわ経済新聞 12月号掲載】

第7回 満寿産業
前に進むために下した決断
「事業承継」と言うと一般的には、親から子などへの企業トップのバトンタ ッチという光景が真っ先に浮かびがちだ。しかし、会社組織の存続という、そもそもの目的から考えると、それだけが唯一無二のソリューションではないということに気付く。
従業員と取引先のお客様を「守る」ため、同業の企業に株式を譲渡し、経営の主導権を任せるといった英断に踏み切 った満寿産業(川崎区)の事例は、ややもすると見落としがちな事業承継に関わる選択肢の「多様性」を、改めて明らかにしてくれた好事例と言えると思われる。

満寿産業は、川崎市工業団体連合会の会長も務める橋本知彦社長の祖父が立ち上げたステンレス部材の加工会社である。発足当初は蛍石などステンレスの副原料の輸入と卸売りを手掛けたが、昭和30年代に進出した部材の切断・加工販売が事業としての金鉱脈をつかみ、大きく花開いた。顧客は戦前から続く老舗らしく、大手上場企業から地元の中小企業まで幅広い。その97%が神奈川県と東京都の顧客区で占められている点も特徴である。
■時代の変化と友の死と
90年に及ぶ満寿産業の経営は、まず祖父の長男が継いだ後、次に、末っ子であった橋本社長の父が3代目として長らくかじ取りを担った。業績的にも安定を続けていた。ところがリーマンショックがそれらを一変させた。ステンレスの原料であるニッケル価格の暴落や、ステンレス需要そのものの激減などが同社を直撃し、多額の負債を抱えてしまったのだ。金融機関はトップ交代による経営の刷新を強く求め、橋本社長が4代目として緊急登板した。45歳の時だった。
橋本社長は金融機関などが示す再生支援プロジェクトにのっとって再建を推し進めた。すると業績はほどなく回復方向に転じ、借金の返済にも筋道が立ち始めた。それは過去、幾多の荒波を乗り越えてきた長寿企業らしい姿だった。しかし「禍去って禍また至る」ではないが、今度は二つの「想定外」が同社と橋本社長を襲った。新型コロナ禍による経営環境の悪化と、幼なじみの急な病死である。とくに後者は、橋本社長と同様、会社を孤軍奮闘しながら率いていた古くからの友だっただけに大きなショ ックを受けた。「自分がもし急死したら、この会社や従業員はどうなってしまうのだろうか」と。同時に、2人いる娘には経営者の孤独と苦しみを味わわせたくないという親ならではの思いも強く帰来した。橋本社長は悩み抜いた末、会社を「売る」決意を固めた。
■グループ入りを決める
従業員などに知られないよう極秘にM&A仲介会社に接触し、1年半ほどかけてマッチング相手を探した。中には満寿産業の不動産だけが欲しいという本音が見え隠れするところもあり難航したものの、最終的には石川県白山市でステンレスやアルミ加工業を営む株式会社BKTへの企業譲渡という形に落ち着いた。同業とはいえ1990年創業の若い会社だけあって、企業文化的にも満寿産業との隔たりは少なくなかったが、商圏が競合せず、何より従業員の雇用が確保されること、借入金が減ることの2点の確約が最終的な決め手となって橋本社長の背中を押した。
BKT側も満寿産業を傘下に収めることで新たな顧客網へのアプローチに道が開くだけでなく、東西に2拠点を構えることでBCP(事業継続計画)の拠点の観点からもメリットは大きいと判断して橋本社長と合意した。
満寿産業のBKTグループ入りは、周囲に衝撃をもって受け止められた。従業員や、古くからの顧客の驚きは語るまでもないだろう。さらに付け加えれば、M&Aの成否を握るPMI(経営統合プロセス)については、きれいごとだけでは進まない。いばらの道と例える向きすらある。ただし、そうした軋轢(あつれき)や障害を乗り越えた先には、新たな経営と事業のビジョンが広がるのもまた、事実である。
もし、企業譲渡を決断しなければ「つぶれていたかもしれない」と橋本社長は、改めて振り返る。「仕事のある会社に手伝ってもらって、商売を続けられるようにした方が良いこともある」と語る言葉には、とてつもない重みが備わ っている。
取材 かながわ経済新聞