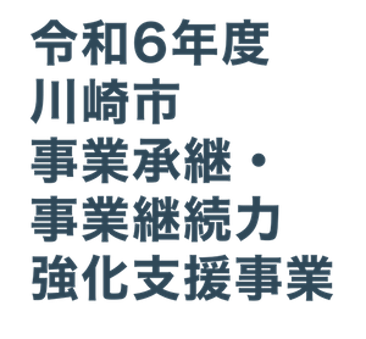【かながわ経済新聞 1月号掲載】

第8回 ナベセイ
事業承継とは、魂を受け継ぐようなもの
■四半世紀一人の肩に
スウェーデンのことわざに「他人を走らせようと思ったら、まず自らよく走ることだ」というものがある。汗水を流さないスマートな評論家風のトップがとかく好まれがちな昨今、株式会社ナベセイ(中原区井田)を前身である有限会社渡辺製作所時代から率いる渡邉敬太社長の半生は、まさに、この言葉の証明に充てられたようだと言っても過言ではないかも知れない。
祖父の昇氏が1958年に創業し、父の敏康氏が85年に継承したタップ加工会社を2001年以降、四半世紀近くにわたって実質的にほぼ独りで率いてきたからだ。この間、親族や友人・知人からのさまざまな縁や支援に恵まれる一方、大口の得意先の倒産やリーマンショックに伴う需要の“蒸発”といった深刻な経営危機にも直面した。その都度、プライドをかなぐり捨ててのどぶ板営業を敢行し、キャッシュフローを改善させるために父親が買った乗用車を売却したり、運送会社の夜間のアルバイトに身を投じたりもした。

■何があっても廃業はしない
普通の人であれば心が折れかねないところであろう。だが、渡邉社長は違った。石にかじりついても会社を続け、大きくしていくことが、志半ばにして病で倒れた父への何よりの「供養」になると考えていたことがまず一つ。そしてもう一つは、幼い頃よりボール盤やフライス盤に囲まれて育った関係で、機械いじりが根っから好きだった。
従って、どんなに苦しくても「廃業」という文字は渡邉社長の頭の中の辞書にはなく、逆に、舞い込んだチャンスをとらえては工作機械を買い増し、事業範囲を金属加工全般へと広げていった。
自ら率先し、明け方近くまで独りで旋盤と格闘する日々が3年近くも続いたという。
だが、そういう姿は、不思議と誰かが見ているものだ。地元企業約300社で構成し、同社もメンバーとして加盟している協同組合高津工友会などから新しい仕事が徐々に舞い込むようになった。15年に母の眞理子氏から名実ともに社長ポストを譲り受けるとそれが加速した。翌16年には、現在、渡邉社長の右腕として取締役副社長を務める片山恵太氏が入社し、取り扱い技術のメニューも拡充した。
■がむしゃらに走り続け
先が見えないコロナ禍の最中も、渡邉社長は走り続けた。20年には念願であった5軸マシニングセンタを導入。22年には横浜市都筑区内に新工場を立ち上げるとともに、現在の社名へと変更した。
足元は半導体や通信関連がけん引する堅調な需要などに支えられ、好業績を背景に、気がつけば従業員の数も26人にまで増えていた。かつての、地獄の窯の淵をのぞいたような鮮烈な経験も良い意味で過去の1ページとなりつつある。
そんな中、渡邉社長が進めようとしているのが片山副社長への「事業承継」計画だ。26歳の時に経営に携わり始めた渡邉社長もはや50歳。気力や体力が今後、いや応なしに減衰していくことが人間の摂理として避けられないことを踏まえ、およそ一回りほど若い片山氏に、10年をかけてナベセイの舵(かじ)取りを徐々に任せていこうという考えである。「事業承継とは、魂を受け継ぐようなもの。誰に引き継ぐかは、『魂を理解している人』が最適だと思っています」と、渡邉社長。ちなみに、渡邉社長のご子息に関しては、早い段階より候補から外れたのだそうだ。
それにしても、同族経営の返上と、長期間を予定する経営のバトンタッチである。これらは、門外漢にはいささか奇異に映りかねない決意だ。だが、これこそ、長きにわたって走り続けた孤独な長距離ランナーにしか分からない「最適解」なのであろう。引き続き、見守っていきたい。
取材 かながわ経済新聞